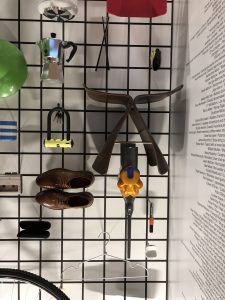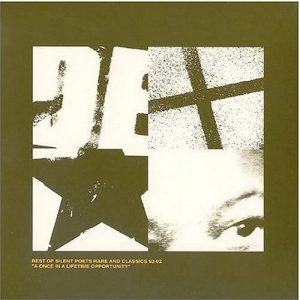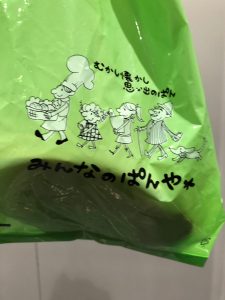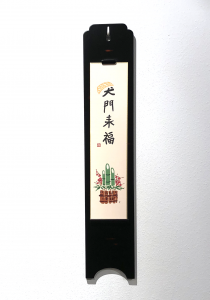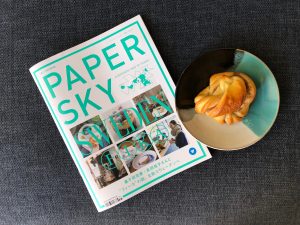すでに本日帰国してまして、時系列で前後しますロンドンの話しが続くと思います。
噂を聞きつけまして、SOHOで一番美味しいという日本食のお店。そこの噂のうどん。この写真にある通りにまだ時節柄ギリギリの”お雑煮うどん”ってのを注文しまして、出てくるまで時間は少し待ちましたが、店中に香るのが鰹節の出汁の香り、日本の店でもこれほど鰹の香りが漂う店はあまりないでしょう。期待が高まります。出てきたお雑煮うどん、カブラや人参、ねぎ、もちと入ってまして、見た目ではカブラが硬いのじゃないかな、と余計な心配をしてました、食べてみると、これがしっかり熱が入ってまして、硬くなく、でも新鮮さも残していて、時間がかかっていたのもこだわりの一つで、火が通りすぎていない感触であっさりと丁度いい感じ、出汁がこれまた薄味で思った通り鰹が効きすぎぐらい効いていて、なんかこの出汁どこかに似てるなと思ったら、京都の仁王門のうね乃に近い。出汁の際立ち方が似ていると。
うどんは讃岐うどんで、茹で時間や水での晒しなどにこだわっているように見えました。当然うどんも美味しいですよ、なんか一気に食べてしまったので、うまかったのでなんかよくわかりません、とにかくうまい。お客さんは大半がイギリスの方、上手に箸を使っています。
朝は早くからやってますね、そのメニューになんとイングリッシュブレックファーストうどんってのがあって、ベーコンと目玉焼きが載ってでてくる、これがうまいと評判、うどんの概念が変わるとか。
とにかく、基本の出汁とうどん玉がうまいから応用が効くのでしょうね、何でも一緒だ。隣で食べていたイギリス人女性、お馴染みさんらしくスタッフと話していて頼んだのが、鍋焼きうどんと鳥の唐揚げ、えーそれ昼から一人食べかい、、と突っ込みたくなる美しい人でした。
鳥の唐揚げがポン酢がけで美味そうではありました、また来ようと思った瞬間でした。ロンドンで日本食食べたくなったら是非、お勧めですよ。
1月 14, 2018