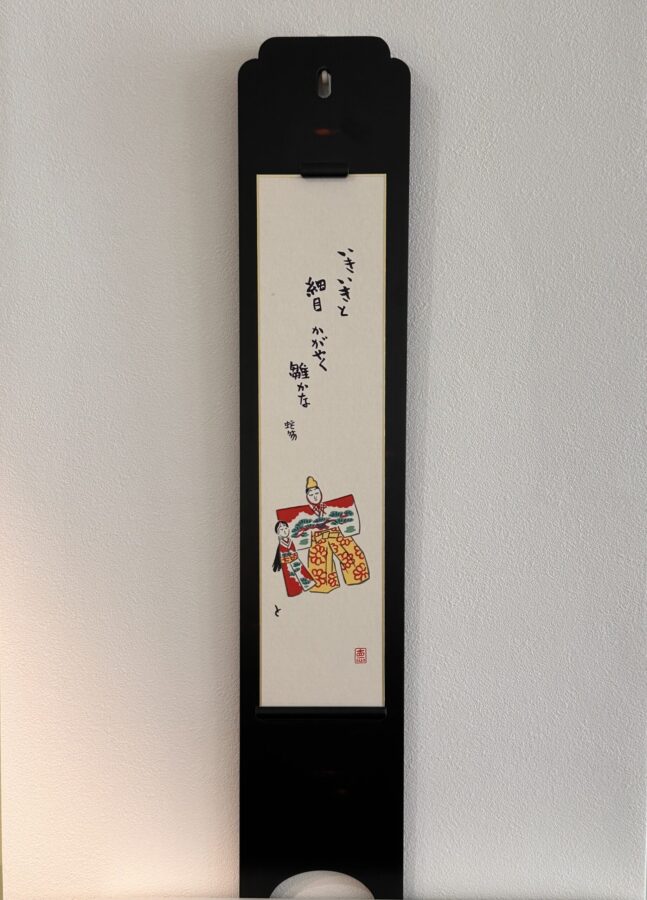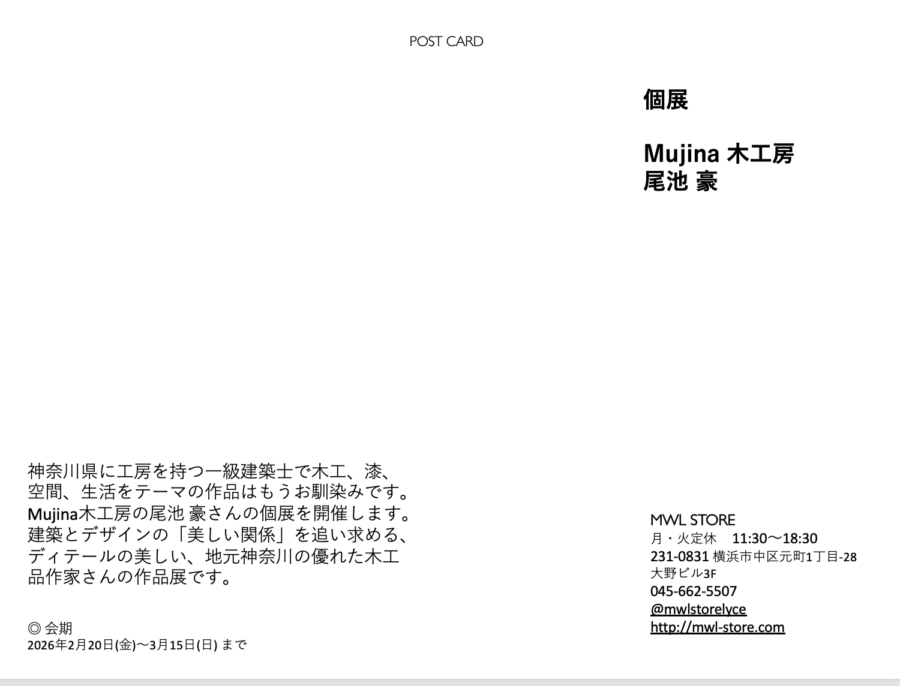本日行ってきました。
横浜市鶴見区大黒埠頭、首都高速湾岸線最大のP A が大国ラウンジとして去年10月にリニューアルされました。
PAの売店が改装されて、とても美しくなりました。2階にはラウンジがありゆったりとしたソファーもありくつろげます。タリーズコーヒーの売店、ラウンジには、元町通りの老舗、タカラダ、フクゾー、キタムラ、横浜馬油、香炉庵 さまの元町の老舗限定商品が並んでいます。





そして一階のレジの横にはMWL STORE の大国PA限定のアイテムとして、お茶缶を積み上げ発売しています。
どうか、大国PAにお立ち寄りいただき、お茶缶を元町土産で、よろしくお願いたします。
3色で各8ティーバッグ、1,782円税込 ここでしか販売しておりません。
大黒埠頭PAは横浜市鶴見区にあります。