7月 22, 2022
7月 22, 2022
神戸のビール

7月 21, 2022
(予告)谷口陶磁器製作所 作品展

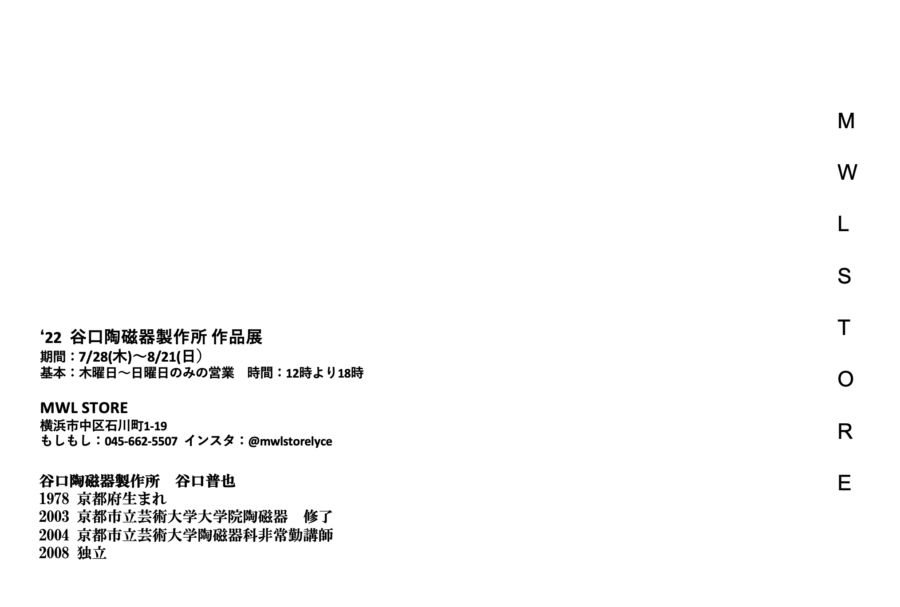
7月 21, 2022
EGG OPEN SAND


7月 20, 2022
22 秋の展示会 第一弾
22年秋の展示会の第一弾が始まります。来週28日(木)が初日になります。アーティスティックな作品200点ほどが並びます。今までとは一味違う陶磁器の数々、伝統と革新の創作の発表会です。
いよいよ、秋からひと月に一人、あるいはひと組の作家さんたちの展示会が2月まで続きます。
大人のプレミアム・シリーズ 開幕します。

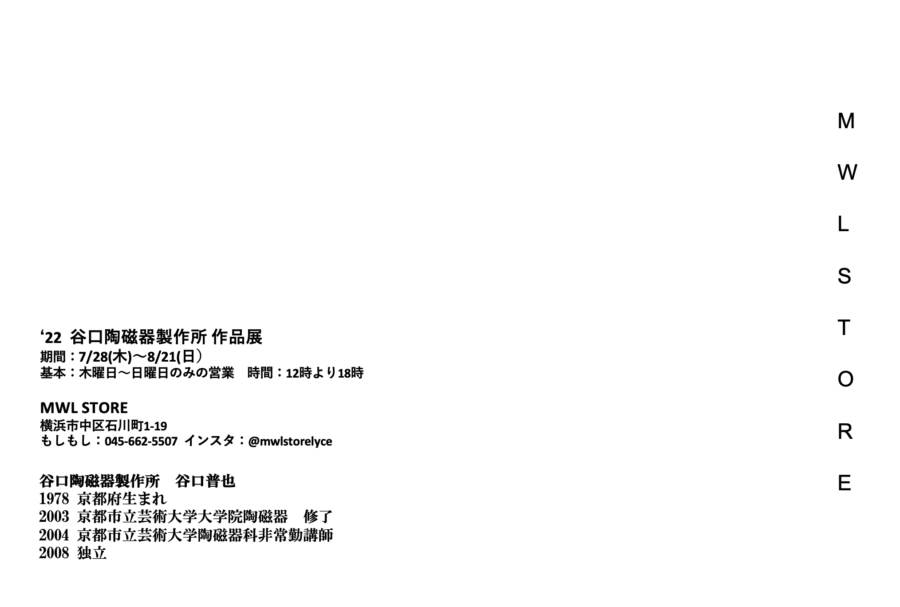
7月 20, 2022
村山光生 白釉・中鉢「素顔のままで」
白というかグレーが正しい、暑い夏に涼しげな陶器である。サビの部分の線とグレーの釉薬の色が、形も含めてフランスっぽいのである。フランスの伝統色として、壁や木に塗るペンキの色の基本色にある色だ。昔からこの色が好きだった、釉薬がぽってりと乗っていて、さらにフランスの陶器のようにも見えるから不思議。じゃぁ、何に使う?そうだなカフェ・オレ ボウルだよね。そんなこと思いながら、村山作品って深いなぁって。木で燃やしている窯は多くはない、やっていても年に2回ぐらいのところが多い、儀式化してるところがほとんど、薪だから出る表情ってのもあるのだろう。それも長々と燃やさずに高い温度まで持っていく、高圧高温で出る表情のあることよ。この器がどうも好きである、気にかかる、個人的に、初めて見た時からそう思っていた。一目惚れってやつよ、理由はそのフランス的な佇まいからだ。パリジャンだね。今ももう30分ぐらい手にして、裏を見ている、美しいのだ。欲しいな。ダイアナ・クラールのLive in Paris の「素顔のままで」が流れている、この器に合うなぁ、この曲。





7月 20, 2022
すり鉢の使い良さとデザインの良さ
おろし器が人気なのですが、実はこのすり鉢がまた素晴らしく、、、大きさが絶妙、洗いやすく使いやすく、底のシリコンがしっかりして不動の地位(位置?)を築く。
色とデザインも秀逸、しまねっこ!
すり鉢、おろし器とも昨日再入荷しています。


7月 20, 2022
LITTLE SCARLET
こんなに小さく愛らしい、リトル・スカーレット種のイギリスいちご。それを一つ一つ丁寧に摘んでいきます。自家農園の限られたいちごです。



7月 18, 2022
金魚
清水小北條の急須 LIKE NO OTHER



あけびで作った国産のコースターはかなり貴重
7月 18, 2022
すり鉢で作るオープンサンド
すり鉢でたまごをレンジでチンする、スライスチーズ、アスパラを乗せて、バルミューダに入れる。卵を茹でるエネルギーはいらない、部屋を暑くする湯気も回らないし、ガスも要らない、エネルギー高騰時の削減策の一つの手法、新しい形のすり鉢でつくる、オープンサンドイッチ。(すり鉢・おろし器は今週分を欠品中です、来週の入荷予定をご予約お願いします)
あまたある、すり鉢
おろし器の中から、
これでいいでなくて
これがいい
の選択、取捨選択する 結果、永く、満足する
それだけを高い思想で創る人がおられて
それだけを見つけて、深堀する 小売店

